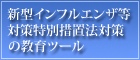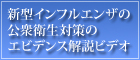|

| ● |
インフルエンザの感染経路として考えられているのは飛沫感染、空気感染および接触感染である。それぞれの感染経路がどの程度の割合で起こっているのかについては不明である。 |
| ● |
感染性期間について考える際に参考となるのがウイルスの排出期間であるが、健康成人の場合、季節性インフルエンザの排出期間は発症前から発症後5日間とされている。小児では排出期間が延びる傾向がある。 |
| ● |
インフルエンザ(H1N1)2009における発症間隔および基本再生産係数はそれぞれ2.5−4.4日および1.1-3.3の範囲で求められている。 |

目次
> 1) 感染経路
> 2) 感染者が感染性を持つ時期
> 3) 無症候感染の有無
> 4) パンデミック(H1N1)2009における感染性パラメータの評価

新型インフルエンザ対策を考えるためには、まずその感染様式を正しく理解することが必要となる。現実的には、新型インフルエンザを起こすウイルスがどのような感染様式をとるかは正確にはわからないので、通常の季節性インフルエンザと同様の感染様式をとるという前提で、主にこれまでインフルエンザに関して得られている感染様式に関する知見についての整理を行なうものとする。さらに季節性インフルエンザと同じような特徴を持ったウイルスによってパンデミックが引き起こされるとしても、季節性インフルエンザと異なり、ほとんどすべての人が免疫を持っていない新型インフルエンザでは感染様式が季節性インフルエンザとは異なる可能性もある。
感染様式のうちでも特に対策を考えるために重要な点は、感染経路と感染性の程度、さらに感染者が感染性を持つ期間である。以下にその知見をまとめる。
1) 感染経路
インフルエンザの感染経路として考えられているのは、飛沫感染(Droplet Transmission)・空気感染(飛沫核感染)(Airborne Transmission)・接触感染(Contact Transmission)の3つの経路である。飛沫感染は感染者の咳・くしゃみなどによって生じるウイルスを含む飛沫(通常直径5μm以上とされる)が他の人の鼻・目・口などの粘膜に直接到達することによって感染が成立するという経路のことである。この場合の飛沫は1〜2メートルの範囲にしか到達しないとされている。これに対し空気感染は飛沫の水分が蒸発し乾燥し、さらに小さな粒子(5μm未満とされる)である飛沫核となり、空気中を漂い、離れた場所にいる人がこれを吸い込むことによって感染が成立するという経路である。接触感染は、感染者と非感染者の直接の接触あるいは中間物を介する間接的な接触により感染する経路である。インフルエンザ感染の場合の接触感染としては、特に汚染された表面(机・ドアノブなど)を手で触れ、その手で自分の鼻・口・目などに触ることによって起こる間接感染が考えられている。
インフルエンザの感染経路としては上記の3つの感染経路が考えられるわけであるが、3つの感染経路がどの程度の割合で起きているかについてははっきりしたデータはなくさまざまな見方がされている。Brankstonらはこれまで発表された論文の系統的な検討を行い、インフルエンザ感染の大半は飛沫感染もしくは接触感染で起きており、空気感染はあるとしても重要な感染経路ではないと結論づけている(※1)。飛沫感染がインフルエンザの重要な感染経路であるという見方は他の総説でも支持されている(※2,※3)。しかし実際に飛沫感染がインフルエンザ感染経路の大半を占めていることを実証した研究は発表されていない。空気感染の重要性については大きく意見が分かれている。空気感染はかなりの程度の割合で起きており新型インフルエンザ対策を考える上でも空気感染対策を念頭に置くべきだとする意見と(※4)、空気感染の存在はこれまで十分に実証されておらず空気感染はインフルエンザ感染に重要な役割は果たしていないとする意見がある(※5)。
空気感染の存在を裏付ける根拠として空気感染を疑わせる流行事例が挙げられることが多い。その中でもよく引用される流行事例としてはアラスカでの飛行機内での感染事例(※6)、1957年のアジアインフルエンザの際の結核病棟での紫外線ランプの使用の有無によるインフルエンザ感染率の違いを比較した例(※7)、さらに高齢者施設での換気の違いによる感染率の比較とした事例(※8)がある。いずれの事例も空気感染を疑わせる事例ではあるが、確実に空気感染があったという根拠としては十分ではないと考えられる。最初の飛行機の事例では、飛行場で飛行機が4時間以上にわたり駐機していた間に一人の感染者から多くの乗客・乗員に感染が広がったと考えられている。この間2-3時間にわたり換気システムが機能しておらずこの間に空気感染として感染が広がった可能性がある。しかし、この間の詳細な人の動きは記録されておらず、飛沫感染あるいは接触感染の可能性も否定できない(※2)。2番目と3番目の事例では紫外線ランプと換気の違いによりインフルエンザの感染率に違いが生じたとするものであるが、違いの生じた病棟間で同じ感染リスクがあったとは必ずしも言えず、これらの事例も空気感染があったという確実な根拠とは言えない(※1,※2,※5)。これ以外の空気感染の有無を検証した研究としては動物実験や人での感染実験の結果がある。このなかにはマウス(※9)やフェレット(※10)を用いて空気感染が可能であることを示した研究などがある。ヒトでの感染実験ではエアゾル化したウイルスは鼻腔内への接種より少ない量で感染を成立させることができたとするもの(※11)や、エアゾル化したウイルスでマスクをしていても感染が成立したとする研究結果(※12)などがある。また鼻腔内にウイルスを接種した場合には自然感染に比べ症状が軽かったことから自然感染では空気感染により鼻腔を越えて感染が成立しているのではないかということを示唆するような結果もある(※13)。また空気中のウイルスRNA量を測定した研究では、インフルエンザ症例が多い時間と場所でのRNA量が最も多いこと、また半数以上の浮遊粒子は4μmであったことが示された(※14),(※15)。さらに感染者の咳に含まれるウイルスRNA量を直接計測したところ65%がやはり4μm以下の浮遊粒子であったが、ウイルスコピー数は大きく分散することが報告されている(※16)。感染経路のメカニズムに関して古典的な疫学的手法あるいは実験医学的な検討だけでは結論を出すことに難しい問題であり、応用疫学的な解析も必要だと考えられる。これらのこれまで発表されたデータを総合すると空気感染はインフルエンザの感染経路としてあり得るが、それが例外的に起きるのか、それともかなりの割合で起きるものなのかは現時点でははっきりとわからないということになる。
直接感染についてもデータは非常に限られており、高齢者施設の流行の際にスタッフの手を介した流行の事例の報告などがあるのみである(※17)。直接感染が重要な感染経路であるとする主な根拠とされてきたのはインフルエンザウイルスの環境中での生存に関するデータである。Beanらのデータ(※18)によればインフルエンザウイルスは透過性のない金属・プラスチックなどの表面では24-48時間生存しており、透過性のある布・紙・ティッシュなどでも8-12時間生存しているとしている。それらの表面から手へのウイルスの移行は金属から手には24時間まで起こりえ、ティッシュからでもティッシュの汚染後15分ぐらいまでは手への十分な量のウイルスの移行が起こるとしている。しかし手に移行したウイルスは5分程度しか生存しないことも示されている(※18)。これらの結果から手などを介しての直接感染は十分可能であると考えられてきた。しかし手に移行したウイルスの生存時間が短いことなどから手を介しての感染は従来考えられていたよりも低い頻度でしか起きていない可能性も指摘されている(※19)。
|
 |


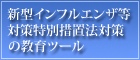
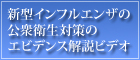








|
本ウェブサイトの構築は、厚生労働科学研究補助金「新型インフルエンザ等新興・再興感染症研究事業」(新型インフルエンザ発生時の公衆衛生対策の再構築に関する研究)の研究活動の一環として行った。
本ウェブの内容に関するご意見・ご質問はpanflu@virology.
med.tohoku.ac.jpまでお知らせください。
|
 |
![]()
![]()